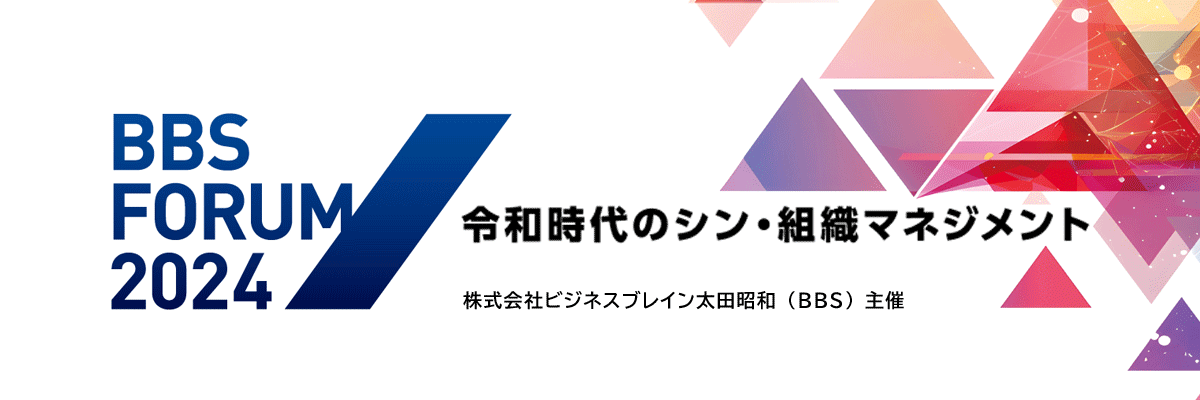
開催概要
日時:2024年11月19日(火) 13:30-19:00
会場:東京コンファレンスセンター・品川
主催:株式会社ビジネスブレイン太田昭和

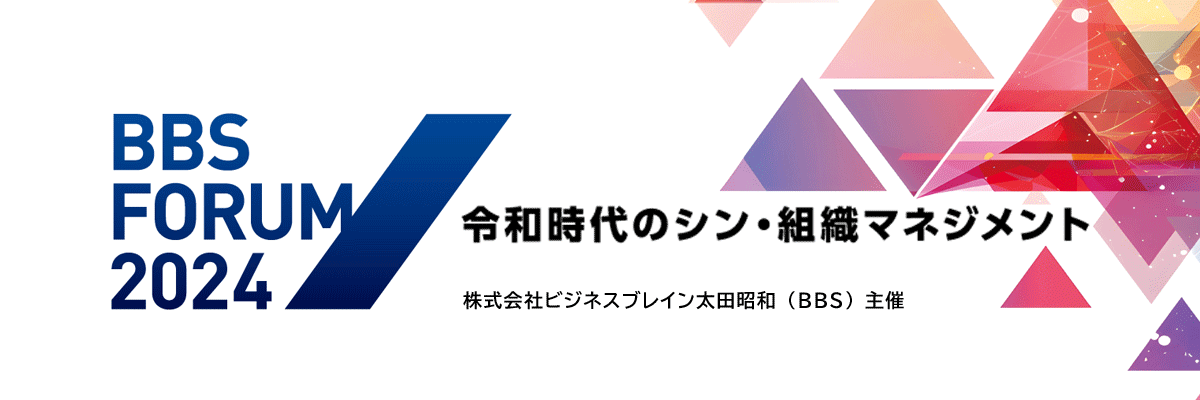
日時:2024年11月19日(火) 13:30-19:00
会場:東京コンファレンスセンター・品川
主催:株式会社ビジネスブレイン太田昭和

あらゆる企業の利益成長・発展に不可欠な人財、人的資本と組織マネジメントをテーマに、「BBS FORUM 2024」を開催しました。イベントでは、当社代表取締役社長 小宮一浩の開会挨拶に続き、ゲストスピーカーをはじめ3名の講演を実施。その後、落語家 九代目 桂文楽師匠とそのお弟子さんである桂ひな太郎さんのお話で和み、例年同様に懇親会も行いました。

桂文楽師匠と桂ひな太郎さんの軽妙な掛け合いに会場が沸く

挨拶に立つ当社代表取締役社長 小宮一浩。
「人的資本経営に取り組むお客様をBBS サイクルによって支援していきたい」とメッセージを発信した


お客様同士のコミュニケーションの場にもなった講演終了後の懇親会
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 副会長/一般社団法人アザレアスポーツクラブ 顧問/学校法人創志学園 日本健康医療専門学校 学校長/株式会社ビーフラット 代表取締役/株式会社ドットピース 代表取締役/NPO法人WASEDA CLUB 専務理事
1986年に早稲田大学入学。ラグビー蹴球部に入部し、日本選手権で優勝。主将として大学選手権で優勝。大学卒業後、サントリーラグビー部で主将を務めるなど中心選手として活躍。2001年に現役引退後、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。就任後5年連続で関東大学対抗戦全勝優勝。大学選手権も3度制覇し、早稲田ラグビー復活の原動力となる。2006年、サントリーラグビー部へ監督として復帰。就任2年目の2007年度にサントリーを初のトップリーグチャンピオンへと導く。2011年よりヤマハ発動機ラグビー部監督に就任し、4年で日本一に導く。2018-2019年シーズン終了をもって監督を退任。2019年6月より公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 副会長を務める。

基調講演に登壇したのは、選手・監督として早稲田大学のラグビー部やサントリー、ヤマハ発動機のラグビーチームを優勝へ導いた清宮克幸氏です。どのような発想や視点で多様なメンバーをまとめあげ、日本一という目標を達成されたのか――ご自身の経験をもとに組織マネジメントの要点についてお話しいただきました。
最初にご自身のラグビー人生を振り返った後、講演はヤマハ発動機での取り組みを中心に進みました。リーマンショックの影響で活動の大幅な縮小が決まっていたヤマハ発動機ラグビー部。プロの監督、コーチ、選手が離脱したことで苦難の時代を迎えていたチームからの依頼を受け、清宮氏は2011年、監督に就任します。低迷していたチームを奮い立たせるため、日本一になることを目標に掲げて選手たちに熱く語ったのが、「ヤマハオリジナル宣言」でした。“ヤマハしかやらないラグビー”をキーワードに、徹底して独自スタイルの構築に取り組んだといいます。
その具体例として清宮氏は、まず“ヤマハしか組まない”スクラムをつくり上げることに腐心したと話します。コーチとフォワード陣を世界で最も進化したスクラムを組むフランスに派遣し、ノウハウを習得させ、そのスタイルをアレンジしてヤマハ独自のスクラムをつくる。そしてもう一つ、選手一人ひとりの持ち味を存分に活かす「ヤマハスタイル」という独自戦術の完成度を高めていきました。清宮氏は、バランスに長けた選手を採用・起用するチームが多いなか、欠点はありながらも傑出した長所を持つ選手を積極的に起用。選手個々人の能力を見た時、能力の高い選手が揃っていなくても、チームとして選手それぞれの特長が発揮できる独自の戦術を練り上げることで、勝てるチームにすることをめざしたのです。こうしたオリジナルのスタイルを突き詰めた結果、ヤマハ発動機は4年後の2014年、日本選手権で優勝を果たしました。
日本一の栄冠を手にして、人生が変わった選手たちには「ヤマハのラグビー部を愛し、チームに貢献するため、責任感を持って行動するロイヤリティ」が芽生えたと語る清宮氏。「選手を活かすオリジナルの取り組みによって一人ひとりの強みを発揮させ、成功体験を通じてチームへのロイヤリティを高める」ことが清宮流のチームマネジメントであり、組織マネジメントの重要なポイントになるとお話しされて講演を終えました。
株式会社ビジネスブレイン太田昭和
取締役 常務執行役員 グループBPO統括 兼 BPO統括本部長
神奈川県逗子市出身。1990年にSEとして(株)西武情報センター[現:(株)セゾンテクノロジー]入社。青年期に喫茶店のテレビゲームとアルバイト先のPOSレジに感化されたことがITの世界へ飛び込んだきっかけだった。入社後は小売・クレジットに関する基幹システムの開発・運用に従事し、経営企画も担当。2012年、給与BPOサービス「Bulas」の責任者となる。2016年、BPO事業の譲渡によってBBSグループに参加し、2024年4月より現職。

BBS講演では、当社取締役 常務執行役員 グループBPO統括 兼 BPO統括本部長の杉野敏也より、「誰がための人的資本経営~情報開示のその先に向けて~」と題した講演を行いました。
企業価値の源泉である人財は“資本”であり、企業が人財教育などにかけるお金は、「コスト」ではなく「投資」という考えが定着しました。有価証券報告書においても人的資本に関する情報開示が義務化され、人的資本経営への関心が高まっています。杉野は、こうした動向を確認した後、人的資本に関する情報開示が求められている背景として、企業の将来性・持続可能性を判断する重要な情報の一つになっていると言及。効果的な開示を行うためのポイントは、「客観的なデータの可視化」「財務情報と非財務情報の統合」「効率的なデータ収集の基盤」の3点であると解説しました。
続いて杉野は、人的資本経営における先進事例として他企業の取り組みを紹介しました。いずれの事例も、学歴や教育年数、保有資格など労働市場で共通して求められる能力を持つ「一般的人的資本」と、その企業で業務を担ううえで求められる固有の能力を持つ「企業特殊的人的資本」を明確に定義していると指摘。そのうえで、経営戦略と人財マネジメントの連携を図っているという共通点があると説明しました。さらに、多様な事業を展開している企業は、事業によって求める一般的人的資本と企業特殊的人的資本の割合が異なることも解説。人的資本経営の要諦は、自社のビジネスモデルをベースに、一般的/企業特殊的人的資本、さらに財務情報も含めたデータを収集して、経営方針との相関を分析すること。これによって成長の基盤となる真の要素を見出し、その要素の維持・強化に必要となる人財を獲得・育成するための戦略を実行することこそが、「情報開示のその先に向けた取り組み」であると提案しました。
講演の後半は、お客様の人的資本経営の高度化を支援するBBSのサービスを紹介。コンサルティング、システムの開発・運用、BPOの各領域において、長年にわたり蓄積した知見とノウハウを活かして多様なサービスを用意しており、ワンストップで提供することも可能であることを説明し講演を締め括りました。
株式会社乃村工藝社
取締役 上席執行役員 コーポレート本部 本部長
神奈川県出身。機械メーカーを経て、2001年に乃村工藝社グループに入社。経営企画や予算管理など、経営管理に関わるさまざまな部門を経験した後、2017年に人事部長に就く。2024年度よりコーポレート本部 本部長に就任。

お客様講演でお話しいただいたのは、乃村工藝社様で取締役 上席執行役員 コーポレート本部 本部長を務める前島隆之氏です。経営企画から人事まで幅広い業務を担当されてきた前島氏から、「社員と経営のベクトルを合わせるために~社員エンゲージメント向上への仕掛け~」と題して、社員エンゲージメントの向上を軸とした同社の人的資本強化の取り組みを解説していただきました。
前島氏はまず、時代の要請に応じて空間創造の可能性を追求し、事業を拡大してきた乃村工藝社様の歴史や強みと提供サービスについて紹介。続いて語ったのが、「じんざい」の表記に対する思いでした。同社では、「じんざい」は材料ではなく財産であるとの考えから必ず「人財」と表記していると説明。成長し続けるためには“社員と経営のベクトル合わせ”が不可欠であり、そのためには会社がめざす方向性に対する“社員の納得感”を高めることが重要になると指摘しました。
続けて、前島氏は社員と経営のベクトル合わせるために実施している多様な取り組みを紹介しました。同社では中期経営方針の策定にあたり現場の第一線で働く社員を参画させたほか、人財教育についても現場起点で職種別専門教育を実施しているといいます。また、自社オフィスのリニューアルに際しては、「社員が自ら“未来の働き方”を先取りしたオフィスをつくる」というコンセプトを掲げ、100名以上の社員が関与。こうして誕生した新オフィスは、第35回日経ニューオフィス賞で「ニューオフィス推進賞」を受賞したことを紹介しました。さらに、経営ビジョンをはじめとする会社の重要方針については、「リアルなミーティングの場で、経営層が社員に対して丁寧に説明することにしている」と話しました。
こうした取り組みもあり、乃村工藝社様では社員の経営理念やビジョンへの理解・共感度は87%を超えているといい、さまざまなバックグラウンドを持つ多様な社員のエンゲージメントが向上したと成果を披露されました。